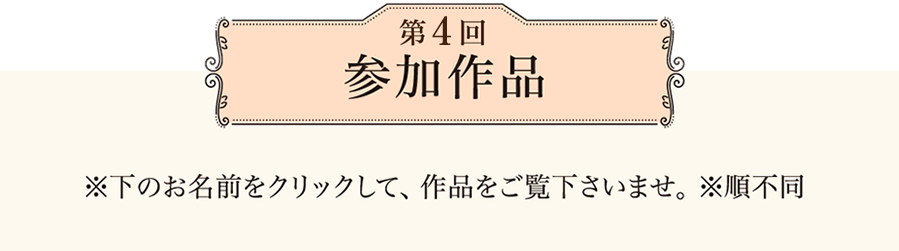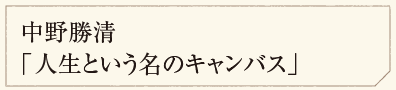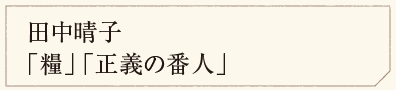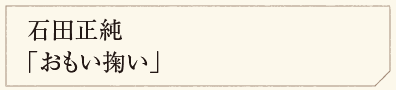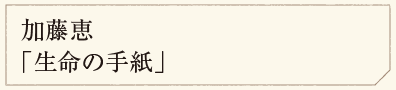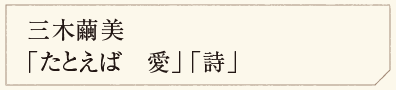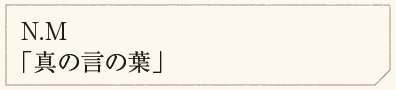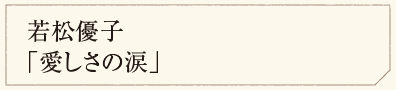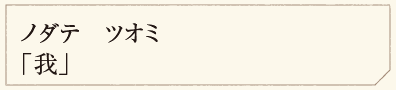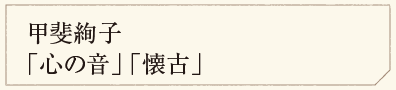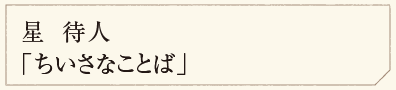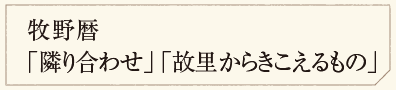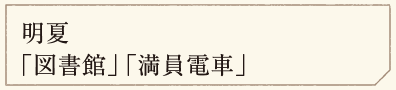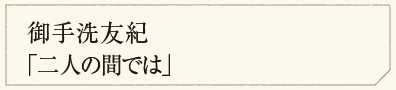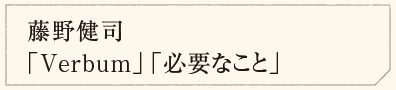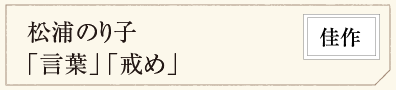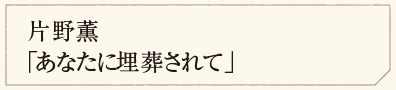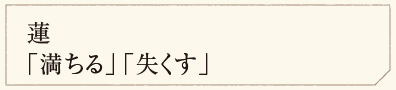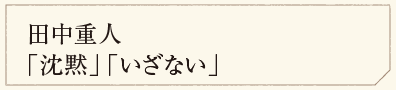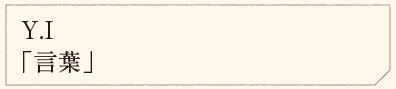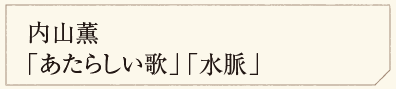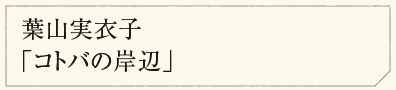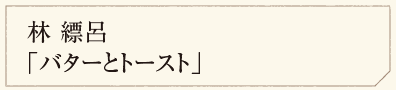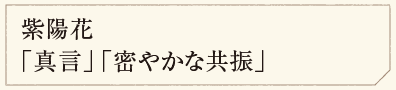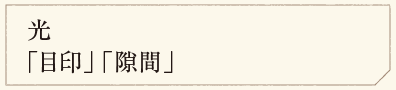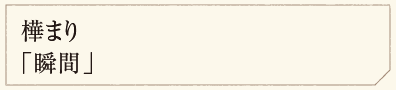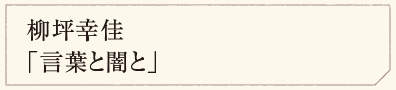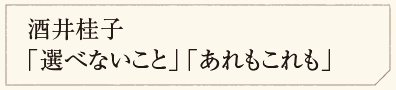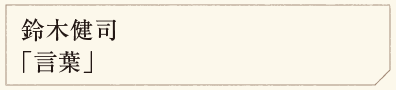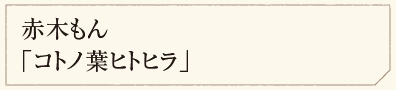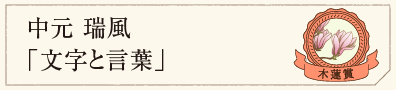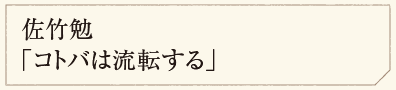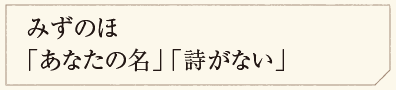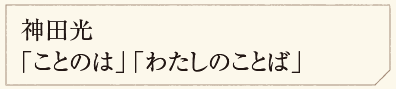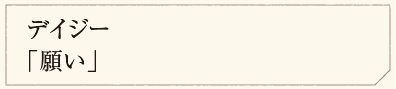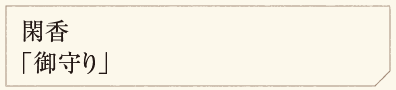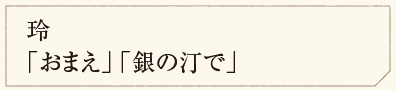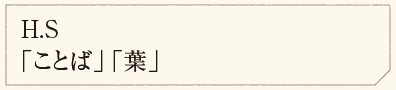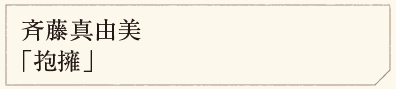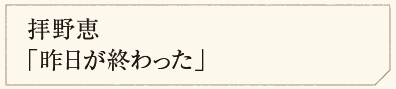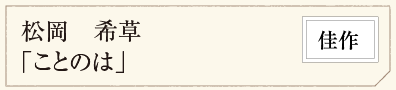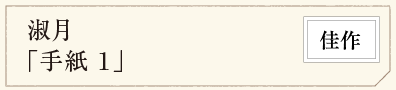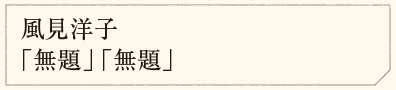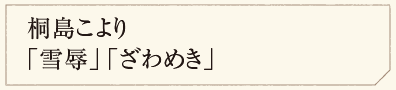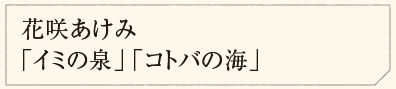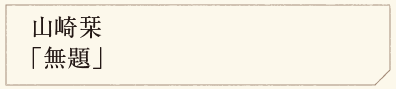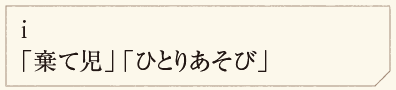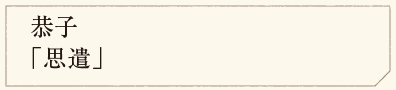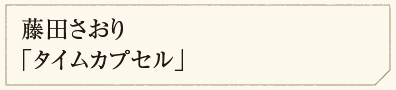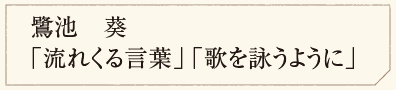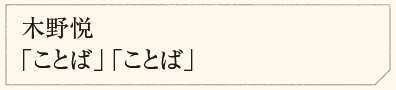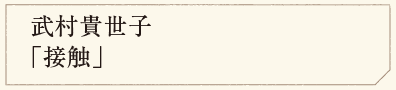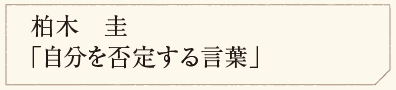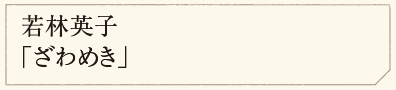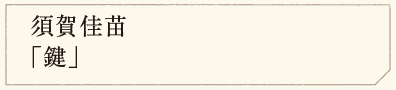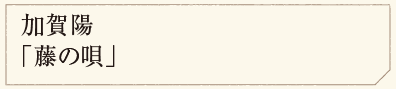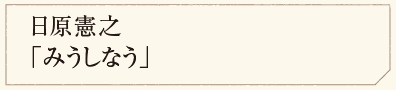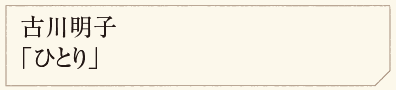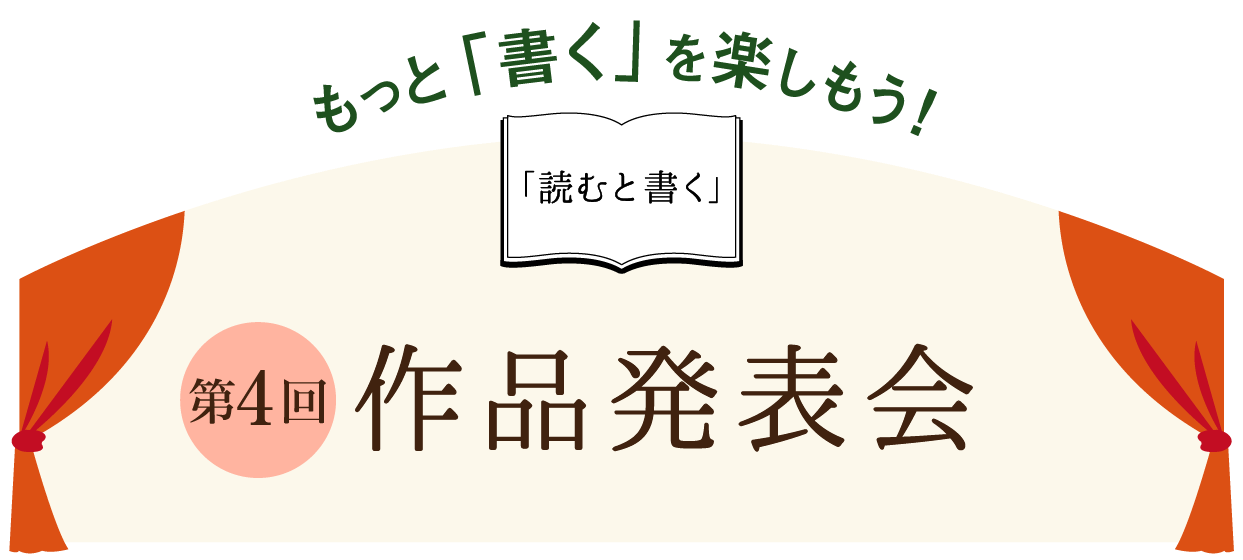
素敵な作品をありがとうございました。
皆様の作品は下記にてご覧頂けます。
《6月7日発表!!》
木蓮賞が決定致しました。
下記をご覧下さいませ。

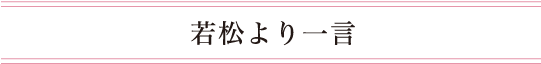
今回も、応募作には強い熱意を感じた。今回で木蓮賞も四回目になるが、回数を重ねるごとに、表現の自由度が広がっていくのもとてもうれしく、また、たいへん頼もしく感じている。
しかし、言葉を主題にした詩を、言葉でつむぐのはむずかしい。ある意味では、もっともむずかしいものの一つかもしれない。
自分にとって大切な一語、あるいは言葉の姿、言葉にまつわる思い出など、さまざまな作品があった。なかでも当選作、あるいは佳作に選んだのは、言葉の本質というべきものに接近した作品、あるいは、接近しようと試みた作品となった。
当初からそうした作品を選ぼうとして応募作を読んだのではない。幾度か読み進めるうちに、言葉の姿や作用よりも、その奥にある意味のうごめき、あるいはその不思議なはたらきに迫ろうとした諸作に独自の魅力があることが感じられてきた。
ことに入選作は、言葉がうごくさまを描きながら、言葉が、不定形の意味へと姿を変えていく道程をありありと描き出しているように感じられた。言葉の音は同じでも意味はまったく変わる。同じ文字でも読む人間の人生観によっても意味はまったく違ったものになる。外形は同じでも、本質において同じ言葉は存在しないのかもしれない、そんなことを感じさせてくれた。
佳作に選んだ諸作は、もう少し早く着手し、作品を「寝かせる」ことができたら、なお独創的なものになったように思われる。四行、あるいは五行という短い詩だが、ひとたび文字にし、それを熟成させ、磨きをかける、という行程には、少なくとも数日以上の時間を要する。
主題を与えられ、詩を書くのもよい。しかし、主題なく、内心から生まれてくる作品にも独自の魅力がある。詩は日常的に書いてよいし、日常的に書くようになると詩的世界はいっそうありありと感じられるようになる。
詩を書くとは、世界を言葉で切り取ることではないだろう。それは、意味というふれることも、見ることもできない実在の姿のまま、言葉という器で受け止めようとすることではないだろうか。
もちろん、実在の方が大きく、言葉ですべてを受容することはできない。しかし、それを切り取ったのではないことが読み手につたわるとき、存在の全体性は、「読む」という行為のなかで新生する。
書き手の手を離れ、読み手とともに実在を新生させようとすること、それが、詩の本質なのではないかと思う。

Q.この企画をどこで知りましたか?
A.登竜門(公募サイト)
Q.選者の若松英輔を知ったきっかけは?
A.同じく
Q.普段から、詩を書かれていますか?
A.はい
Q.何年くらい書かれていますか?
A.11年程
Q.受賞された作品を書かれたときのことを教えてください。
A.「言葉」と言えば、無限大の表現が出来るけれど、使い方を誤ればアッという間に凶器になり得るものという印象がありました。凶器であり、狂気や侠気を表現出来る。不思議な事です。ただ文字の並びというだけなのに。それを詩に起こしました。
Q.受賞されたお気持ち、感想をご自由にお書きください。
A.今まで詩や俳句や短歌でいくつか佳作をとったことはありますが、こんな事は初めてで、知った時には思わず声を上げて喜び舞い上がって仕舞いました。これは、今までの私が報われる事であり確実にこれからの支えとなるものです。
Q.ご自身にとって大切な1冊をあげるとしたら?
A.自費出版した詩集を挙げたいところですが、谷崎潤一郎先生の「刺青」。あれは小説でありながら詩のようです。語り出すと長くなるので割愛しますが、私はあれ程美しいものを知りません。
木蓮賞受賞、おめでとうございます。
中元瑞風様には、若松直筆の詩をお送りさせて頂きます。
〈参加賞〉
ご参加頂きました皆様に参加賞と致しまして、音声メルマガやeラーニングでご利用頂ける割引パスをお送り致します。