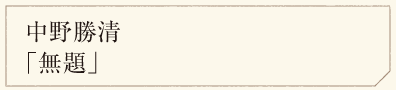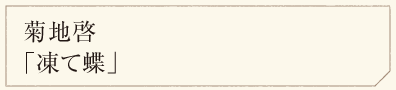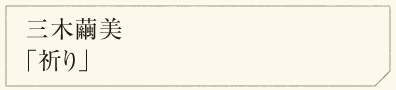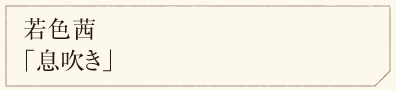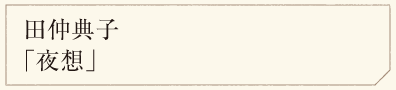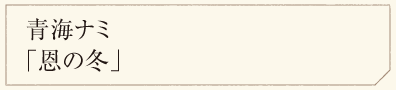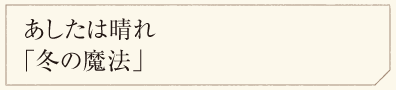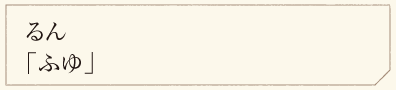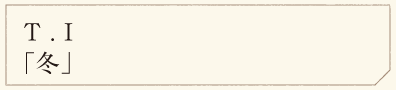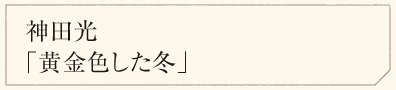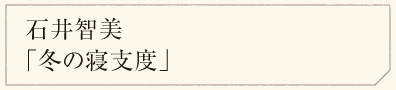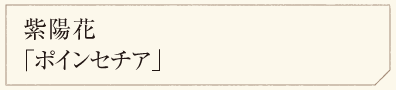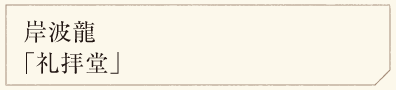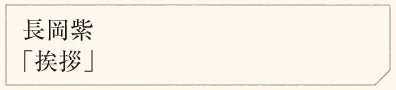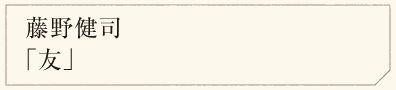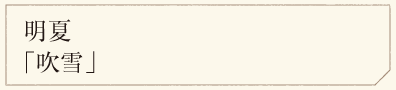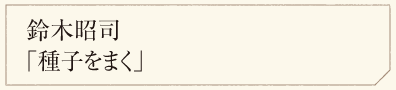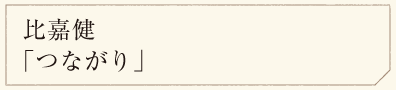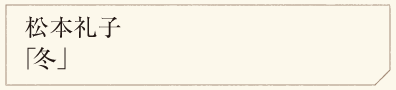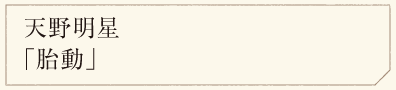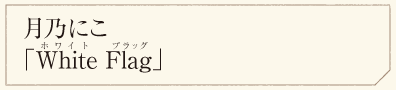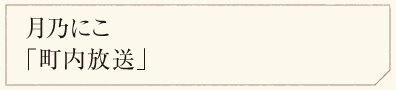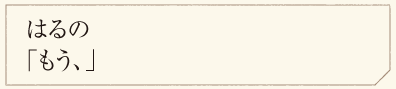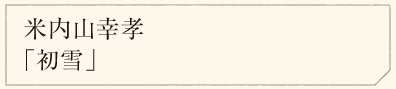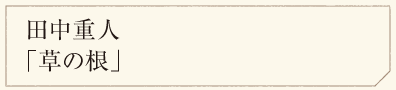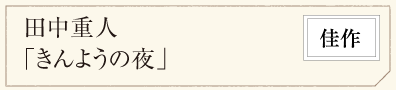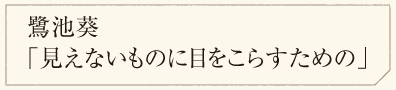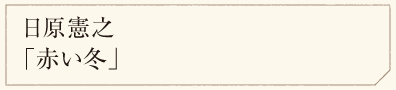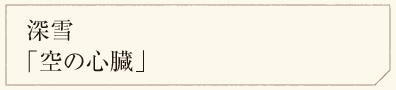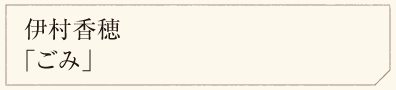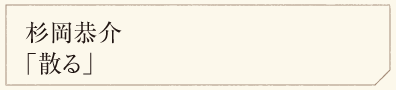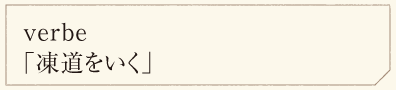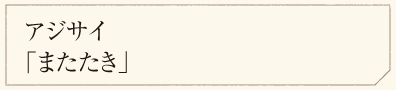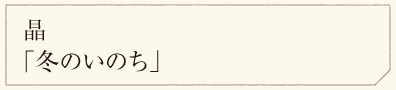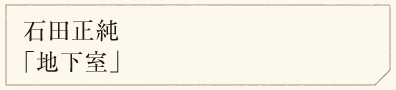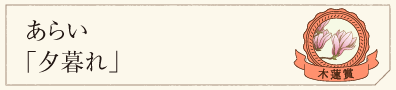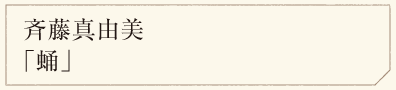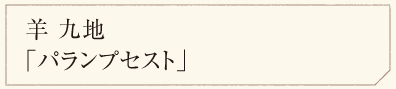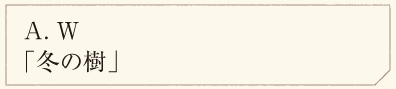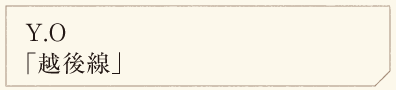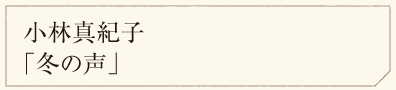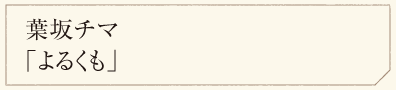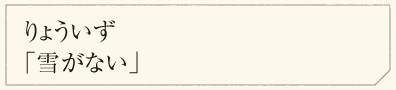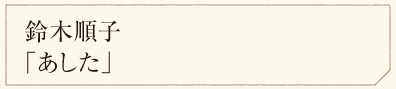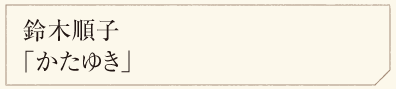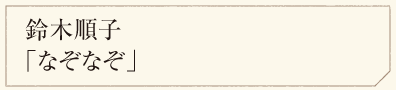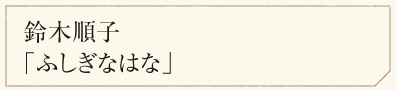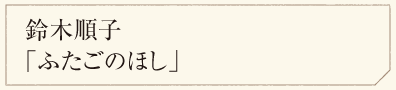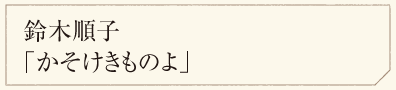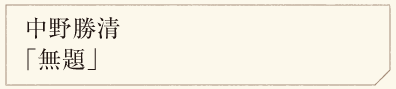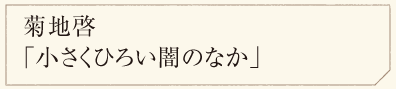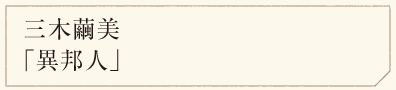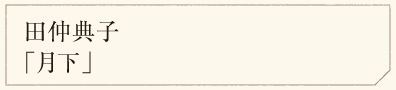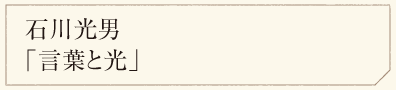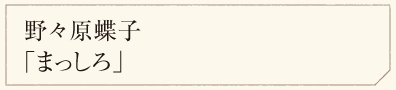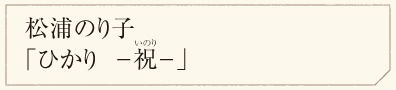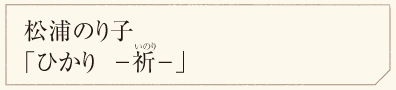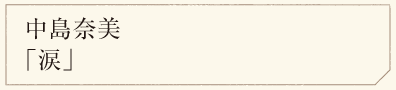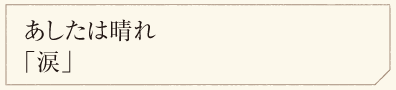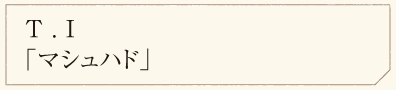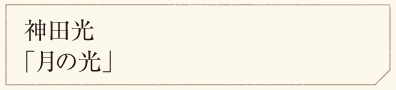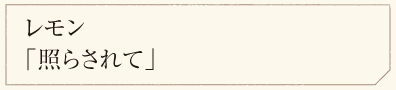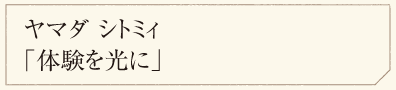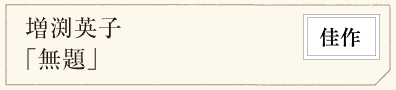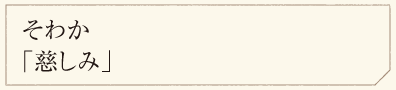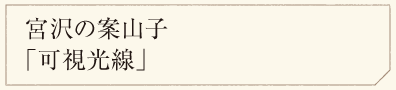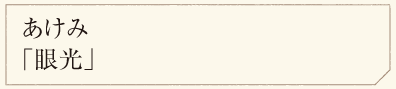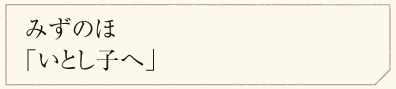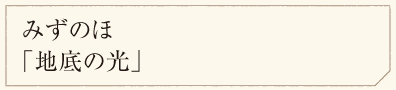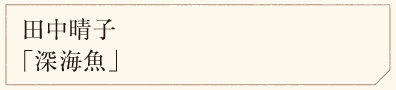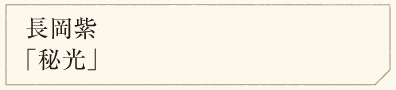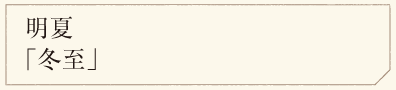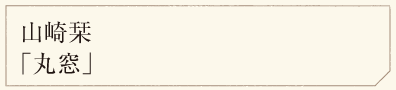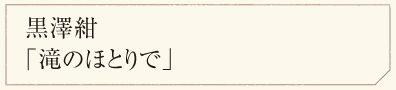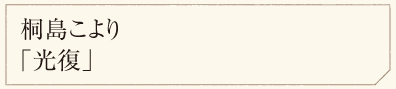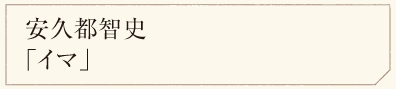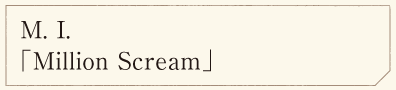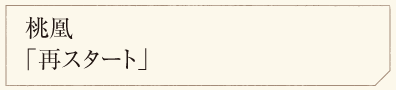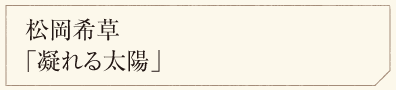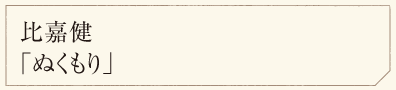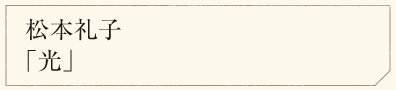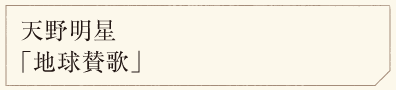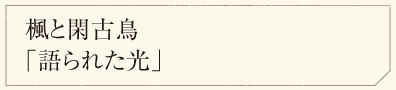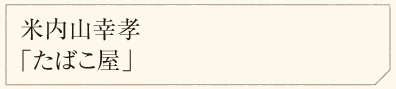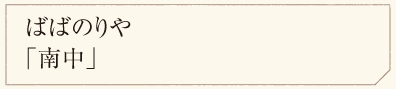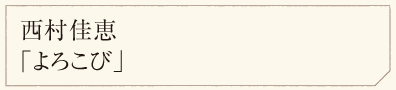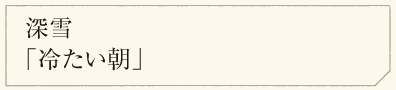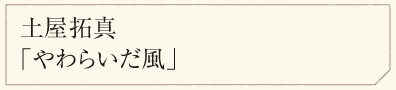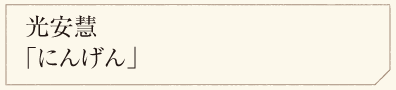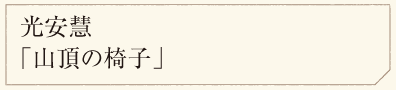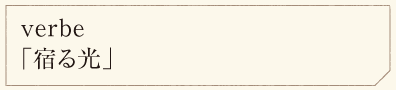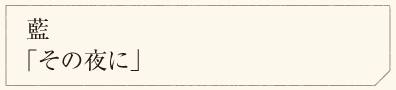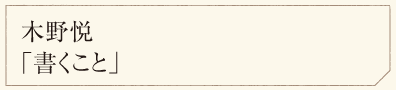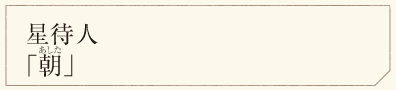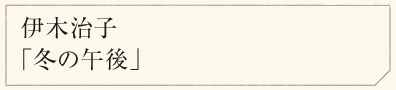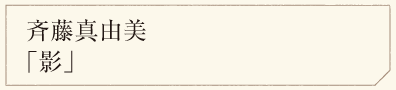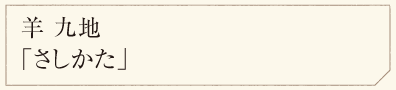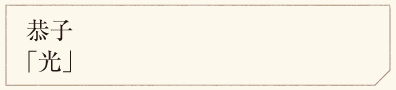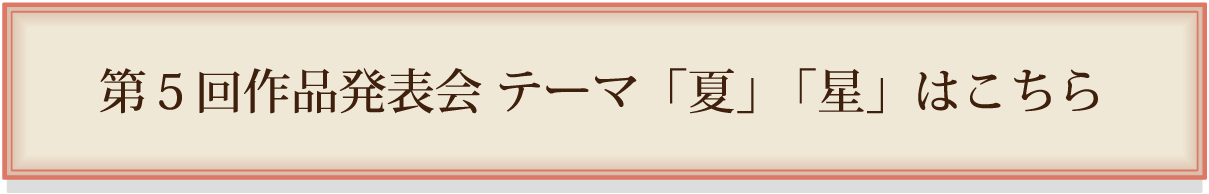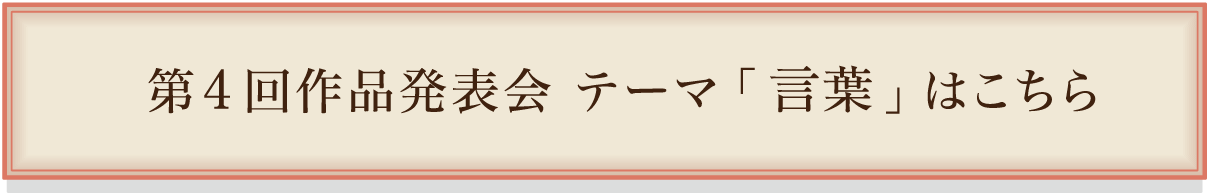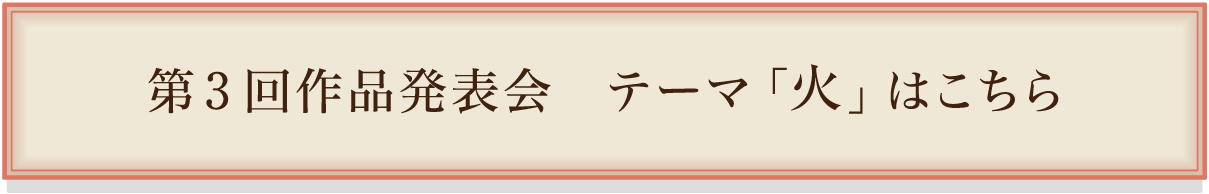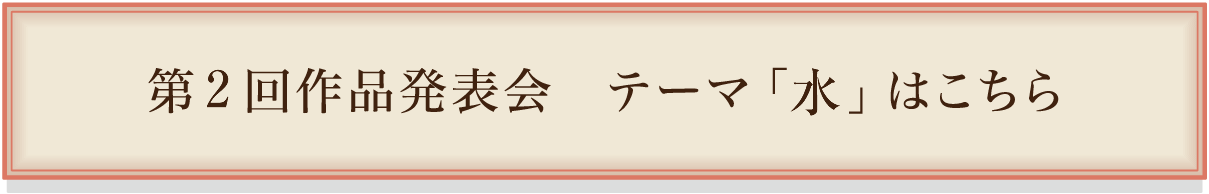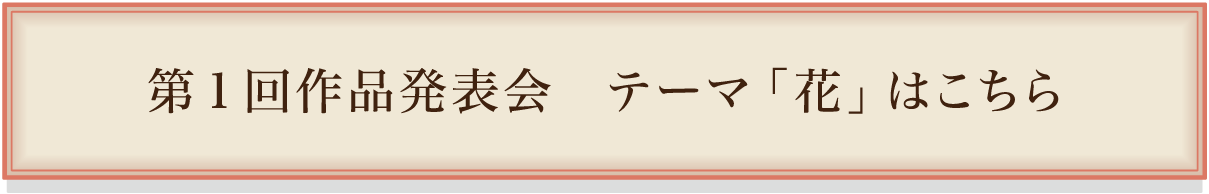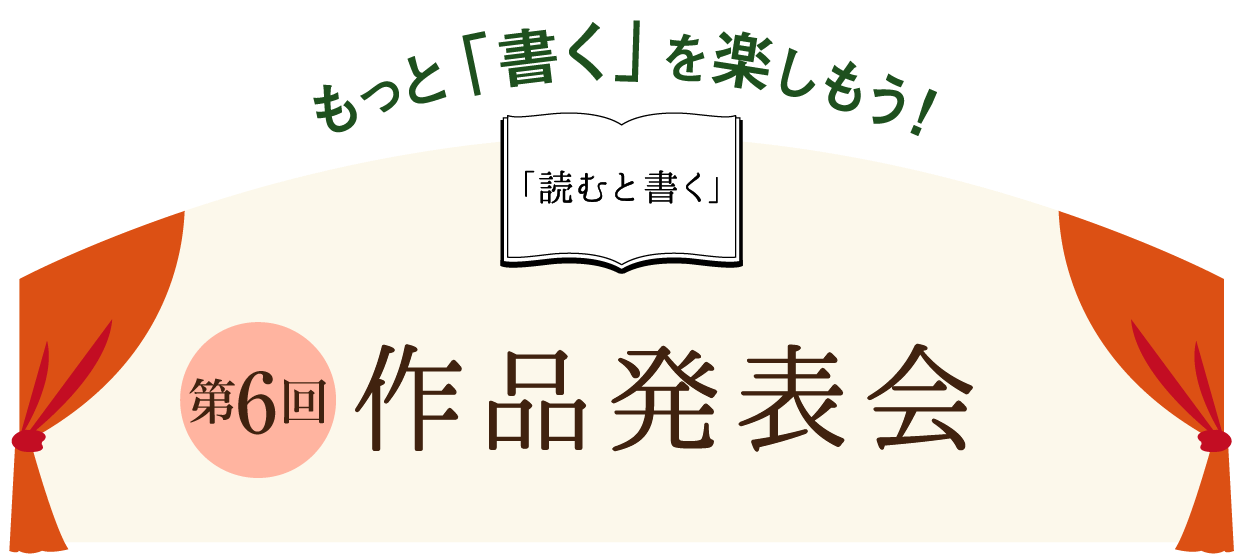
素敵な作品をありがとうございました。
皆様の作品は下記にてご覧頂けます。
《2月27日発表!!》
木蓮賞が決定致しました。
下記をご覧下さいませ。
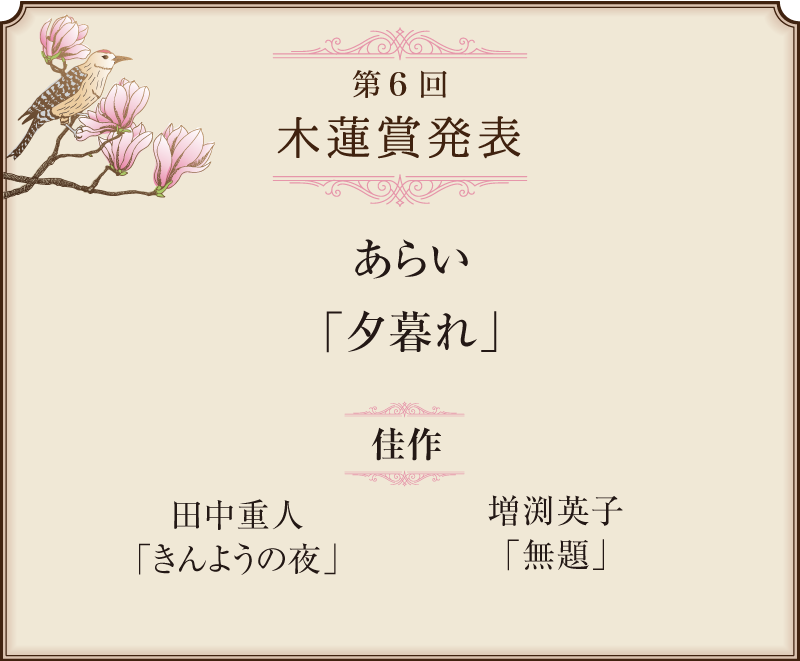
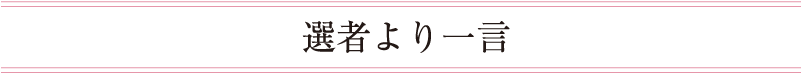
今回も80人、118篇の作品の応募があった。応募数もさながら、それぞれの書き手の意気込みが深まっていて、じつに喜ばしく、たのもしい心持ちで選考をすすめた。
考えてみれば、今回のテーマだった「冬」も「光」も、その到来を感じることができるが、そのものにはふれることができない。応募された作品を読みながら、改めてそう感じていた。
結果としても、ふれることはできないが、たしかに存在する何かを描き出した作品を選んだように思う。
詩とは、言葉にならないものを言葉によって、現出させようとする営みだともいえる。読み手は、書かれた言葉と共に、書き手の心のなかにある、「書き得ないもの」を感じる。少なくとも私にとっては、「書き得ないもの」の表現は、詩を読むときに不可欠なものになる。言葉としてはよく描けている。だが、描き切れているものは、ここでいう「書き得ないもの」の読後感がもの足りない。
今回の木蓮賞となった「夕暮れ」は、色という非触覚的なものを、「ふれ得る」ものとして描き出すことに成功している。そっと添えられた「薄紅色」という素朴な色彩を指す言葉も、ここでは、ほのかな、しかし、かけがえのない熱の表現になっている。
佳作を二篇選んだ。
「きんようの夜」は、この書き手の詩における文体の誕生を感じさせる。詩の文体は一つでなくてよい。音楽における楽器のように多様でよいが、そこからある調べが響いてこなくてはならない。
もう一篇の佳作は「無題」だが、一行詩として読み、選んだ。「祈り」は「光」のように私たちの世界に遍在する、というのだろう。とても印象深い作品だったが、それゆえにもう一段の深みを感じたいとも思った。
詩は、書き切ることのできない営みだともいえるかもしれない。書き切れない手ごたえを深めていくことで、詩境は、育まれ、深まっていくのだと思う。(若松 英輔)
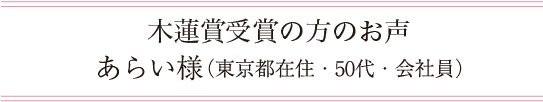
Q.この企画をどこで知りましたか?
A.いつも送って頂いているメール
Q.選者の若松英輔を知ったきっかけは?
A.朝日カルチャーセンター新宿の「井筒俊彦」に関する連続講座に参加していた際に、日本思想の回を若松先生が担当して、その時に先生を初めて知りました。
Q.普段から、詩を書かれていますか?
A.「読むと書く」関連の講座をきっかけに様々な詩を読むようになり、ときどき、特に旅行や出張などで遠くへ出かけた際に、その時の印象などを詩の形式で記すようになりました。
Q.何年くらい書かれていますか?
A.3年ほどです。
Q.受賞された作品を書かれたときのことを教えてください。
A.昨年末、山陰地方の日本海側の街を訪れたときに見た夕日が、共に見た人との思い出と合わさり、脳裏に残り、写真では表現できないような印象を持ちました。そのことを後日、一人でいるときに、詩の形式で日記のような気持ちでノートに記しておいたものです。
Q.受賞されたお気持ち、感想をご自由にお書きください。
A.自分の気持ちを素直に記しただけのものでしたが、応募にあたり、5行詩の形式にした時点で、改めて自分の想いが整理され、見返すことのないアルバムのように手元を離れた気持ちでいました。受賞の連絡を頂いた時、自分でどんな詩を書いたのかはっきり思い出せないぐらいでしたので、意外であるとともに、何か人ごとのような気持ちがしました。極めて私的な言葉から、何かを受け取って頂いたと思うと、とても不思議な感じがします。
Q.ご自身にとって大切な1冊をあげるとしたら?
A.井筒俊彦 イスラーム文化 学生時代から時々読み返してきた唯一の本。これがきっかけとなりもっと広い世界に出会うことができました。
あらい様には、若松直筆の詩をお送りさせて頂きます。
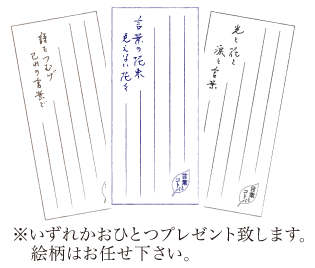 〈参加賞〉
〈参加賞〉
なお、ご参加頂きました皆様全員に、参加賞として、「若松の言葉入:オリジナル一筆箋」をお送りさせて頂きます。
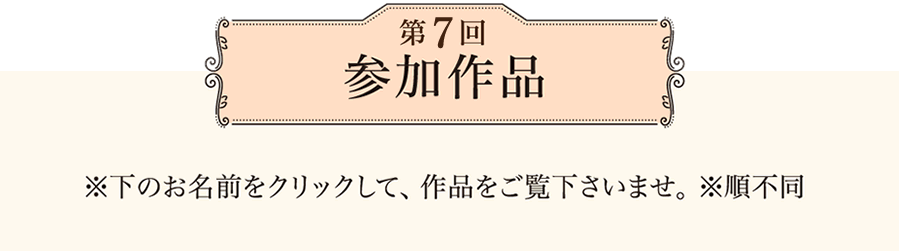
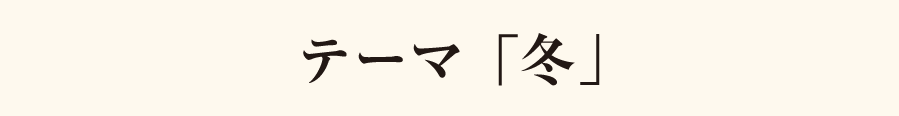
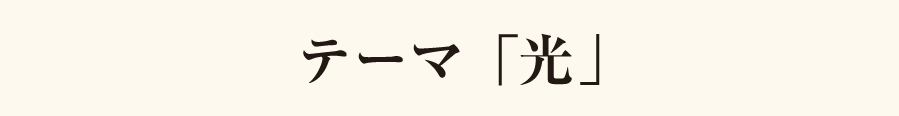
〈過去に行われた発表会〉