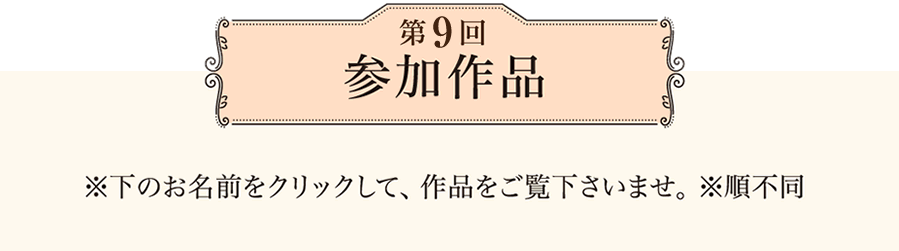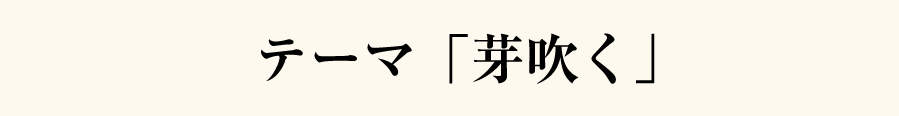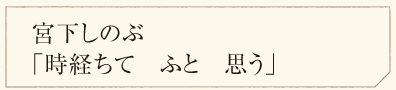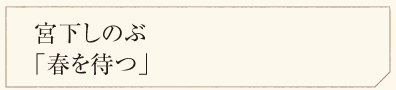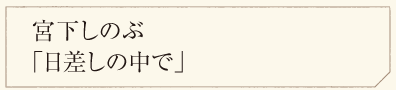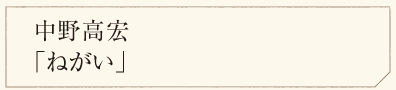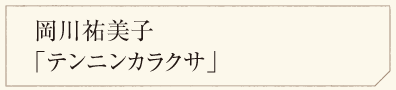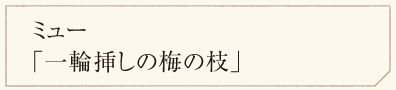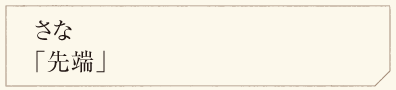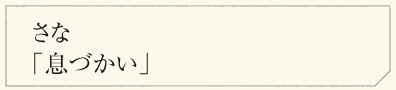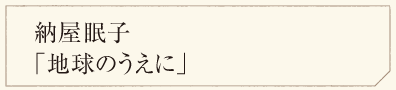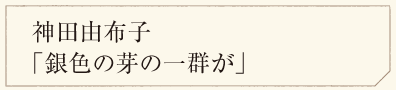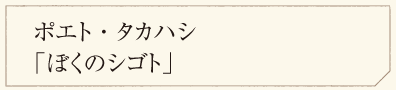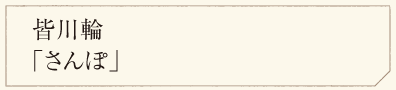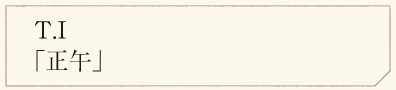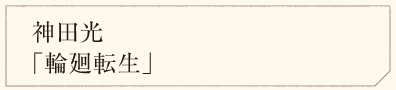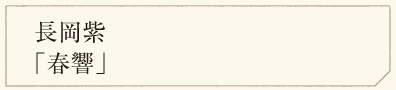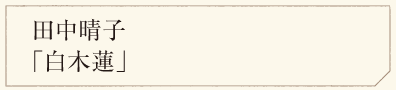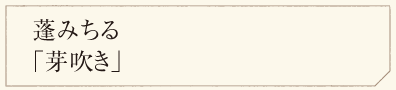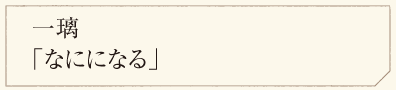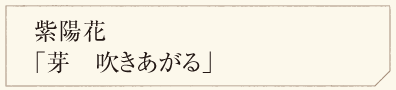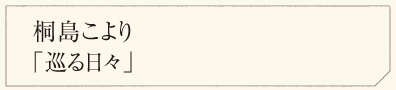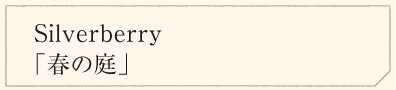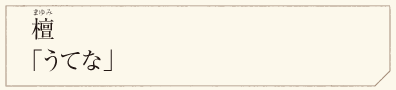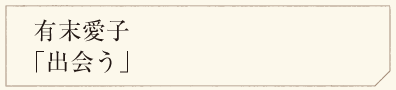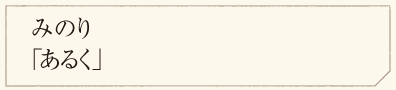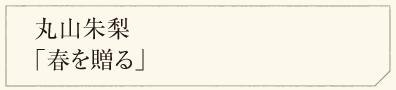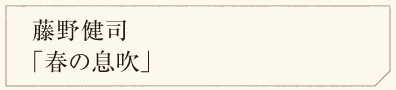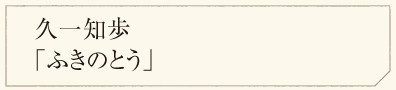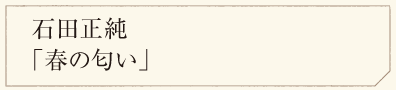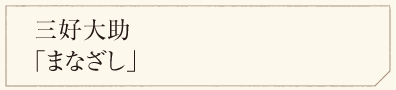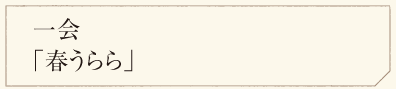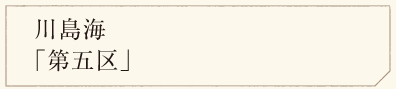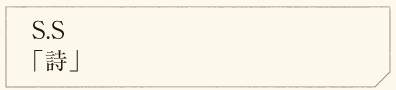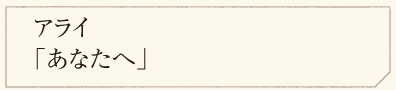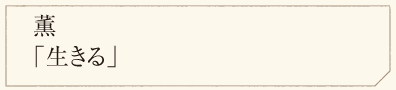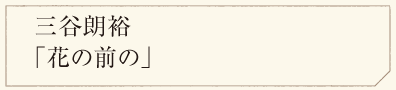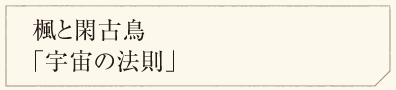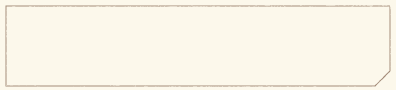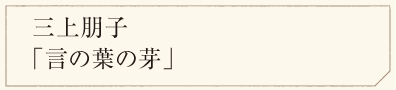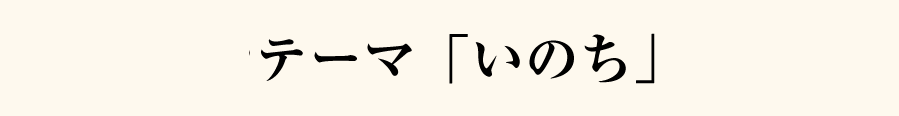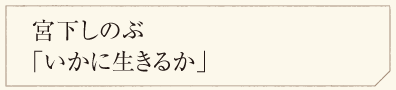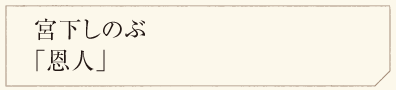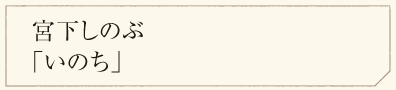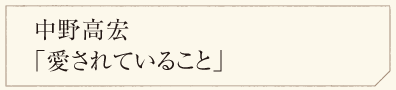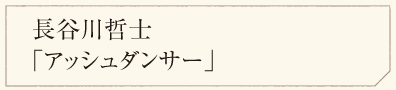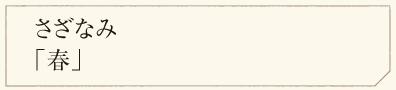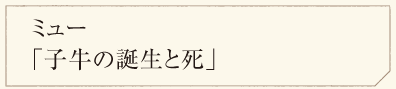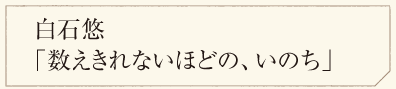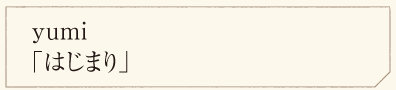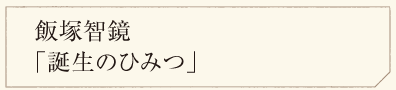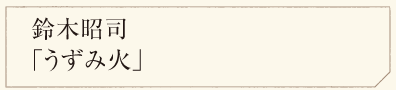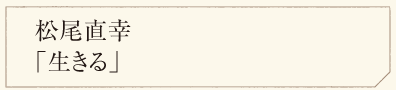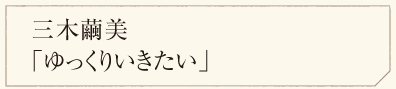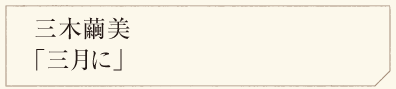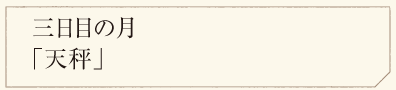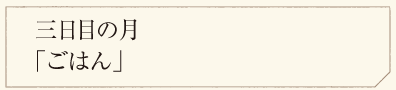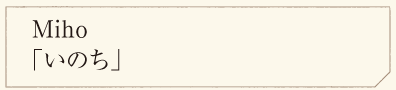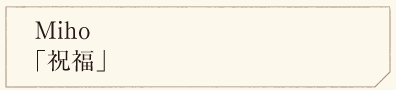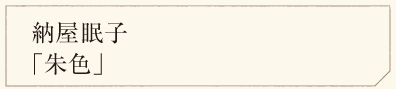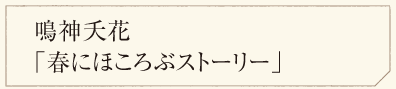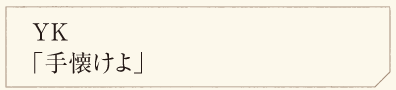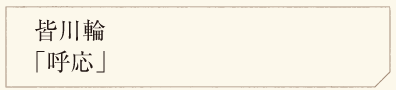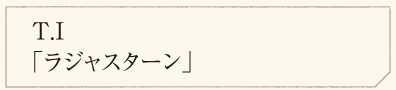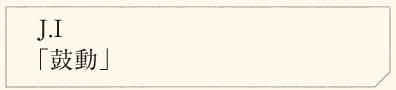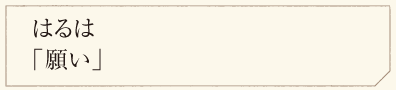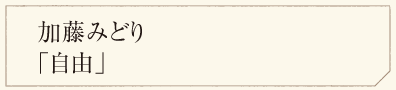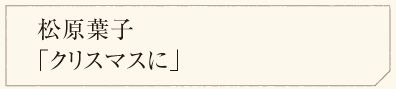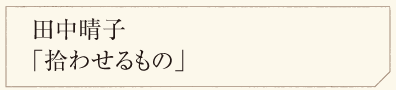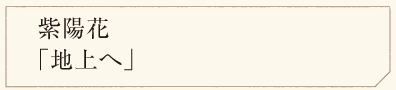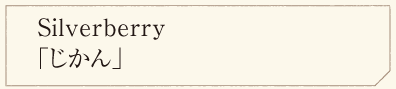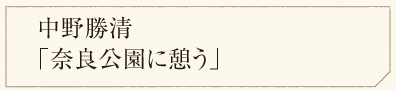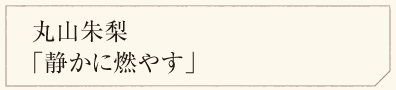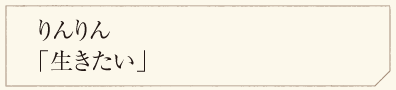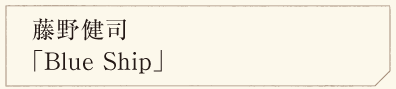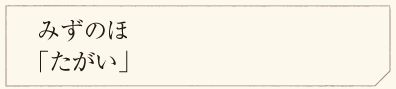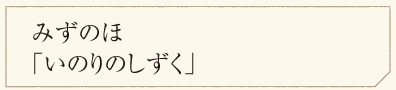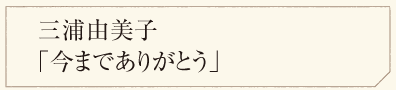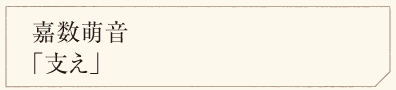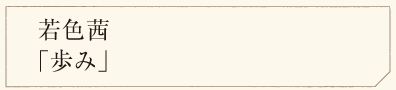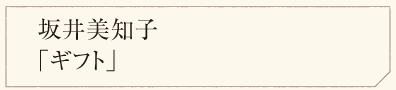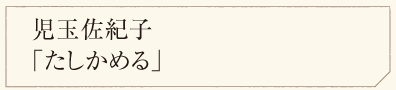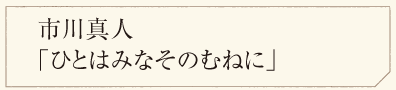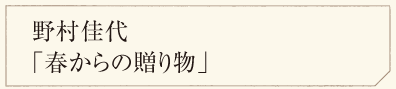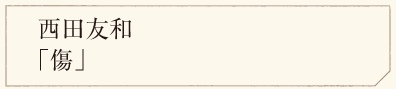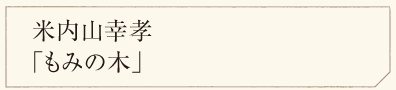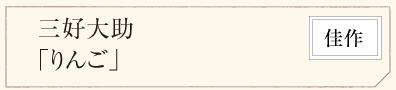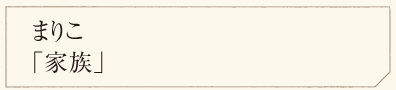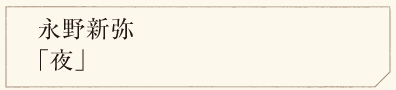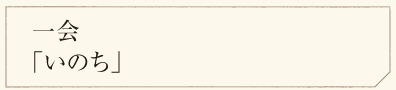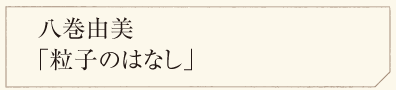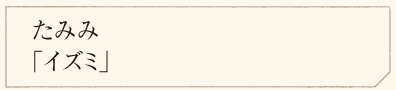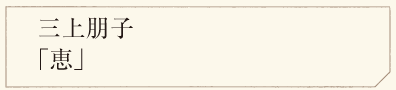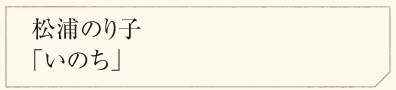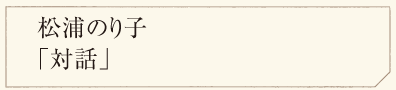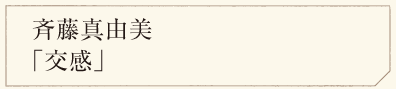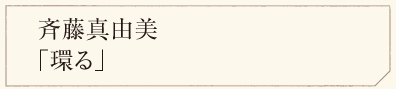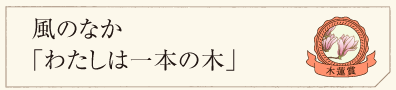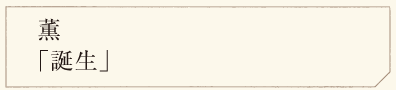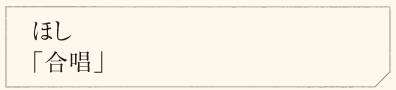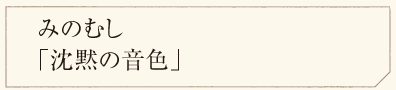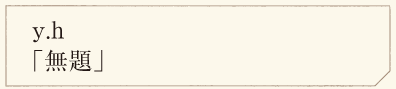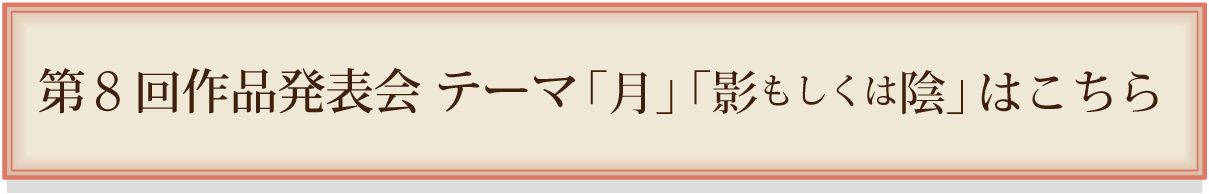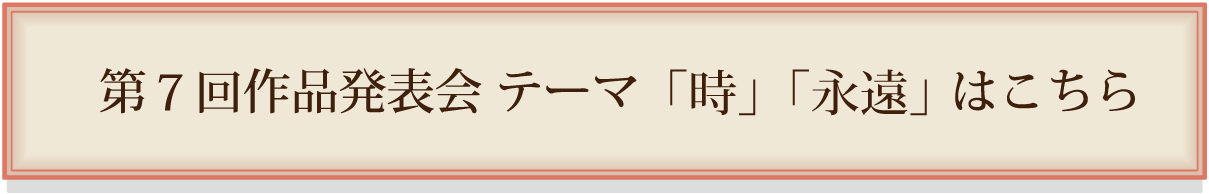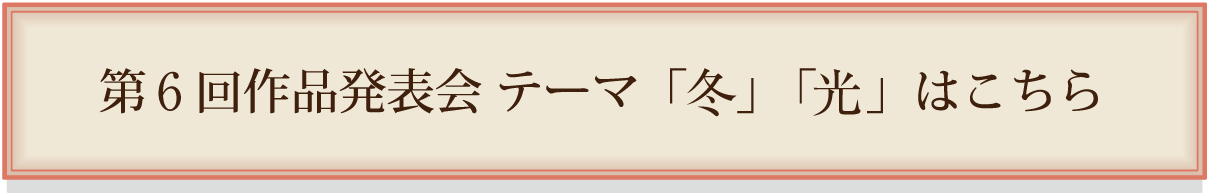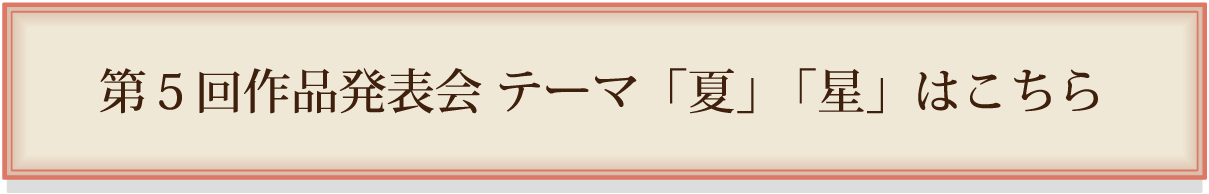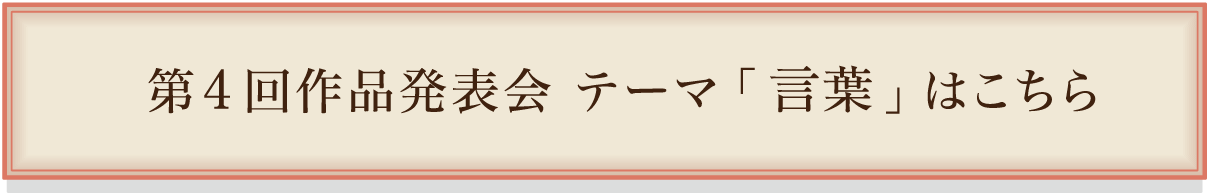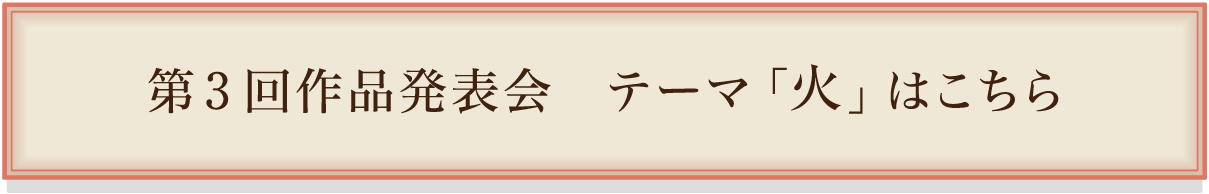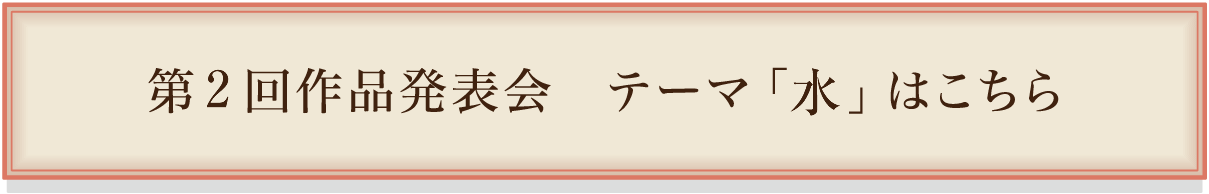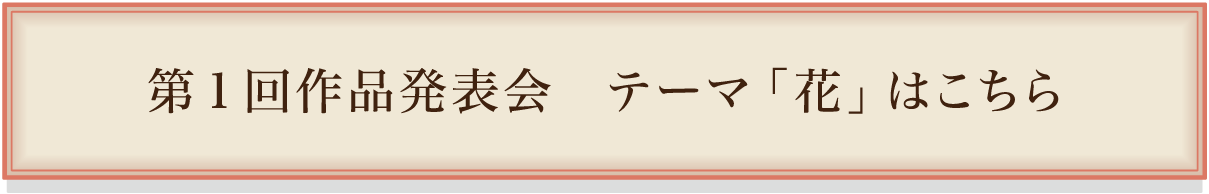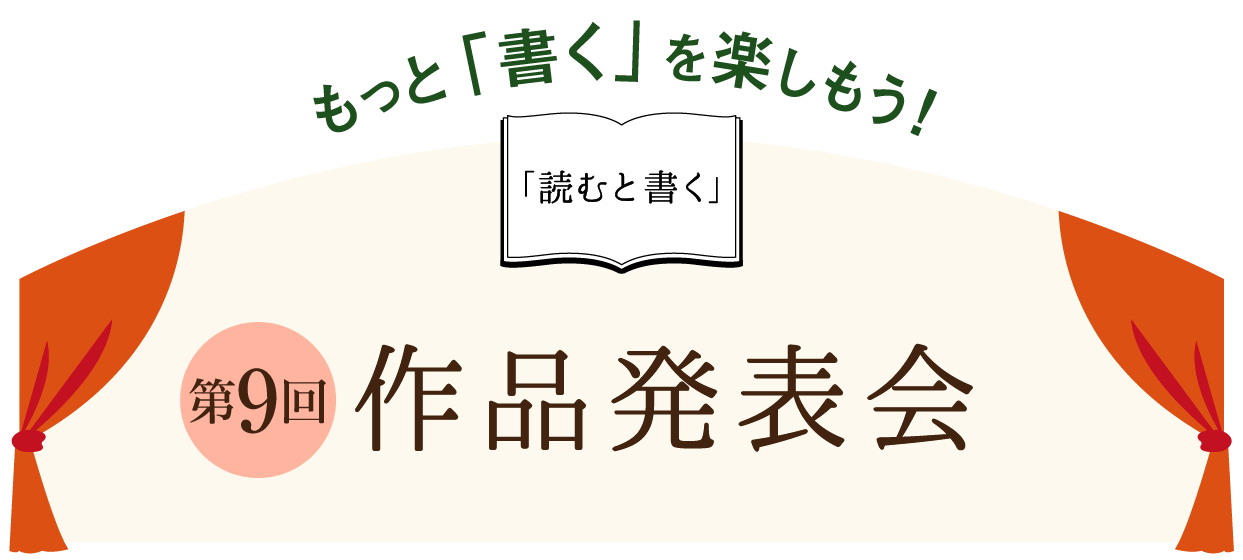
素敵な作品をありがとうございました。
皆様の作品は下記にてご覧頂けます。
《4月28日発表!!》
木蓮賞が決定致しました。
下記をご覧下さいませ。
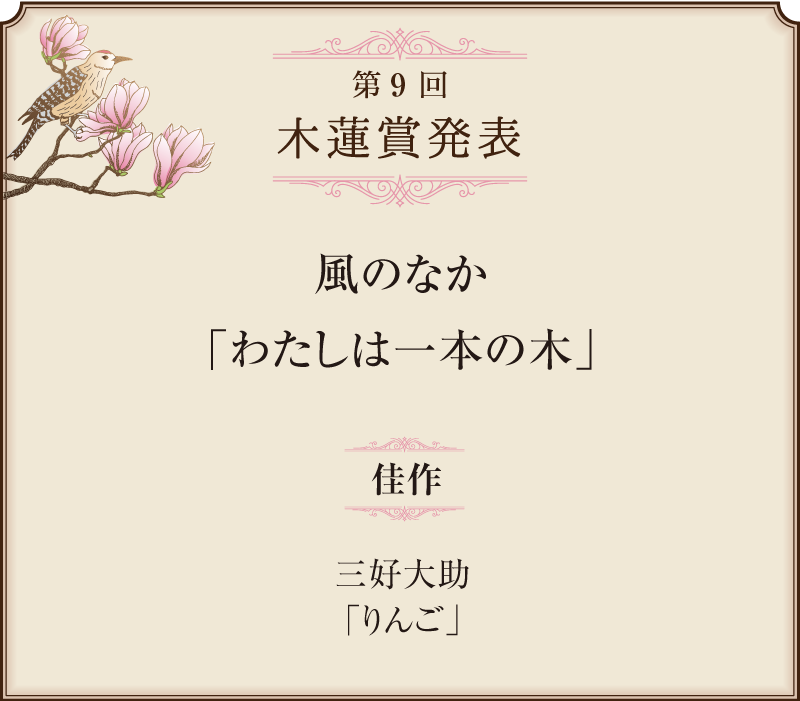
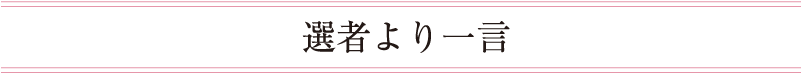
詩は、長すぎても短すぎてもいけない。そんなことを思いながら、今回の応募作を読んでいた。
作品の精度は回を重ねるごとに高くなり、言葉にも熱がある。素晴らしいことなのだが、惜しかったのは、筆力の加減において均衡を欠く作品が多かった点である。ほとんどの作品に詩情を豊かに感じるのに、言葉の多寡がその発露を拒んでいるのである。
主題に関して言えば「いのち」においてよき作品が多く、「芽吹く」において困難が見られた。受賞作と佳作がともに「いのち」から出ているのもそのことを端的に示している。
「いのち」という主題をめぐって詩作するとき、必ずしも「いのち」という言葉を用いる必要はない。読む者がそこに「いのち」を感じ得るかどうかが問題であり、さらにいえば、手や頭でつむがれたものではなく、「いのち」のほとばしりが文字になっていればそれがもっとも好ましい。
受賞作は、ある人は、加筆補正の必要を認めるかもしれない。しかし、この作品が「いのち」の筆によってつむがれたことを否む者は少ないだろう。受賞作の作者――選考者は、応募者の名前を知らされておらず、そのまま選評を書いている――は、詩作という行為よりも「いのち」のことわりに深く通じているように感じられた。
文学における未完成は、しばしば完成されたものを超えるちからを有する。むしろ、それが文学の秘義なのかもしれない。おそらく、この作品の作者は、作品を完成させようとは思わかったのではあるまいか。それよりも、「いのち」の今を自分が生きた言葉でつむぎだそうとした、その試みのあとが、作品とその余白に「いのち」を与えている。
佳作の候補は複数あった。そのなかで選出した作品が一段優れているように感じられたので、一作にしぼった。
りんごは、これまでの多くの詩人や画家によって描かれ、さまざまな事象を象徴してきた。作者はそれに「ずっしり」として「孤独」を見た。「わたしの孤独」をりんごに投影する者はいるだろう。しかし、この作者はそこに「りんごの孤独」と「わたしの孤独」の「和音」を聞く。
「孤独」を感じる詩情の射程は確かである。しかし、「甘い」という形容詞がかえって「和音」の響きを弱めているようにも感じられた。この一字を何か、真実の色に置き換えることができたら、孤独の光はもう一つの時空を照らし出したかもしれないと思った。
(若松 英輔)
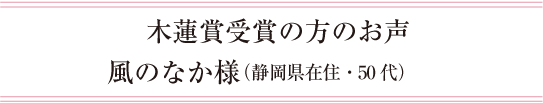
Q.この企画をどこで知りましたか?
A.読むと書くHP
Q.選者の若松英輔を知ったきっかけは?
A.どの作品という明確な記憶はなく、影響を受けた作家を巡っていくうちに自然と若松先生の著作も本棚の一角に収まっていたという印象です。
Q.普段から、詩を書かれていますか?
A.子どもの頃は書いていましたが、今は書いていません。
詩を読むことはずうっと好きでした。
「読むと書く」で気の向く講座を受けて、また書き始めました。
Q.何年くらい書かれていますか?
A.書き始めて半年位?
「読むと書く」の未提出課題がたまっています。
Q.受賞された作品を書かれたときのことを教えてください。
A.3/14午前3時に実父を救急搬送し、4/6に私が住む町へ転院させる状況の狭間で。
病院とのやりとり、医者とのやりとり、本人から送られてくるメールや電話での声。
奇跡的に命はとりとめたものの、病気の根治的治療は行わないということを選択するのに、コロナ禍ということも手伝って、病院は経営が逼迫している。高齢患者であっても、危険を顧みず積極的治療を行えば保険点数は稼げる。万が一その治療で命を落とすことになっても、「ご寿命でした」という切り札があるので家族から責められることもないだろう。立場が違えばでてくる言葉も異なるやりとりのなかで、私にとっては反面教師でしかなかった父の人生を振り返る作業ができたのは、『読むと書く』の木蓮賞の課題という一つの、全く日常とはちがった世界があったおかげでした。
何気なくそこここに立って揺れている木というのは、自由に動くこともできず、傷を負ったり、自然災害によって切断されてしまっても、絶えることなく生きて、若葉を芽吹かせたりもする。その誕生においてそもそも親を選ぶことができない人間の不自由さと一本の木の一生が重なりあって、今回の言葉がでてきたように思います。
どんな木であれ何かに害を及ぼすことよりも、時にすさんだ気持ちを慰め、憩わせてくれ、自然に対する感覚を取り戻させてくれる存在でもある(老)木と「老父」というのを重ね合わせたようにも思います。
Q.受賞されたお気持ち、感想をご自由にお書きください。
A.揺さぶりをかけられる言葉を他者から多く投げかけられる中で、本人も家族もできることなら多少なりとも納得できて、苦しみや痛みから解放された最期を迎えるための選択を行えるよう準備する役目を与えられたように自覚したので、そんな状況からででてくる正直な気持ちを言葉にして記録しておきたいという作品でした(時間切れの中で作った)から、思いがけず木蓮賞をいただけたことに感動しました。
谷川俊太郎氏の「へをひってびっくり」ということばあそびうたが思わず頭に浮かんだ(それほど受賞のお知らせは頭に全くなかった)のは、粗削りだけれども自分の中からでてきた言葉だったから、自分の体からでた音なのに、我ながらびっくりする小動物や赤ん坊のような気持ちに一瞬なったのかもしれません。これを励みに、自らの課題をあきらめずに追っていこうという気持ちになれました。
Q.ご自身にとって大切な1冊をあげるとしたら?
A.金剛出版 森さち子『症例でたどる子どもの心理療法---情緒的通いあいを求めて』
言語的交流をもてない自閉症の7歳の少年との5年にわたる心理療法についての記録です。
安全基地としての母親像をこころの中にしっかり根付かせ、情緒的対象恒常性を保てるような、日頃の交流がいかに人間にとって大切なことなのか。名づけようのないこころに渦巻く快・不快からさまざまな複雑な感情を名付けていく過程について、そこに重要な意味をもって働くことば コトバ 言葉の大切さについて考えさせてくれる本だと思います。
西洋の科学的態度(個別の臨床記録から普遍に通じる法則や規則を考えだしていく方法と伝統)と、縛りがある一方でその縛りにきゅうきゅうとしないで、柔軟に使いこなしていくには、臨床家の深い迷いと思考過程の果てにあるという現実を目のあたりにできる記録だと目を見開かれる思いで読みました。